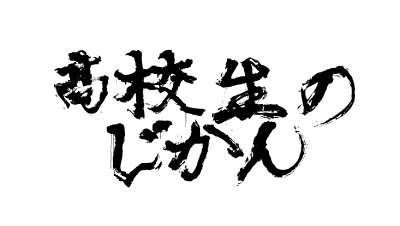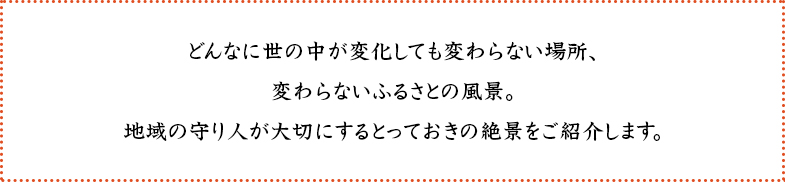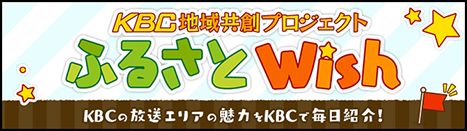【貴金属加工職人❷】「宝石を包む」川野良太さん
2026年02月22日

北九州市小倉北区、旦過市場のほど近いところに、工房「ゆびわのこと」があります。
貴金属加工職人の川野良太さんは、たった一人で指輪の加工や修理、制作作業を行っています。
「一人でできることは全部、もう何から何までやります」と語り、顕微鏡をのぞき込み小さな宝石と向き合います。

川野さんが得意とするのは「彫り留め」という伝統的な技法です。
地金を彫って宝石を埋め込むための爪を作り、一つひとつを丁寧にとめていく繊細な作業。
幅わずか2.5ミリのリングに1.3ミリのダイヤモンドをとめていきました。
顕微鏡がなければ見えないほどの緻密な世界で、確かな技術が美しい輝きを生み出します。

「できることなら、誰かにこの技術を伝えたい。」川野さんの願いです。
ジュエリー職人を目指す人はたくさんいるはずだと感じており、この素晴らしい技術に触れる「きっかけ作り」から始めていきたいと考えています。
希少な技術を守りながら、その伝承にも意欲を燃やす川野さん。
その原動力は「人に喜んでもらえる作品作りをしたい」という純粋な思いです。

川野さんが未来に残したい風景は「小倉の街並み」です。
大きすぎず、どこへ行くにも便利なこの街の規模感が好きだと語ります。
そして何より「人が温かい。街に住んでいる人の個性が感じられる。」と、小倉ならではの人情味あふれる雰囲気を大切に思っています。