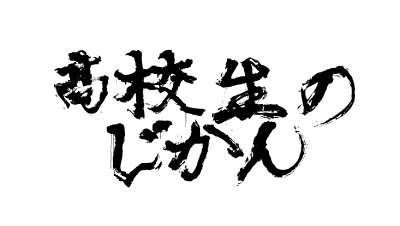線状降水帯について考える その4
番組で紹介した情報
2024年06月26日
(太田)「KBCラジオ みんなで防災!」KBC解説委員の太田祐輔です。
(百市)百市なるみです。
(太田)毎週この時間は、あなたの命を守る防災について考えていきます。
(百市)今日のテーマ「線状降水帯について考える その4」です。
(太田)まさに梅雨末期のこの時期に全国各地で大きな災害をもたらしている線状降水帯についてお送りしています。
(百市)きょうはどんなお話ですか。
(太田)この線状降水帯の発生の頻度についてお話します。
気象庁気象研究所の資料によりますと、毎年の集中豪雨と短時間大雨の発生回数を、長期的な傾向を見る上でのトレンドラインを引いてみて1976年と2020年で比較すると、集中豪雨の発生件数は2・2倍、短時間大雨は2・0倍およそ2倍に増えています。
ということは集中豪雨、短時間大雨をもたらす大きな原因とされる線状降水帯の発生件数もそれだけ増えていると考えるのが自然です。なぜ、それだけ発生件数が増えたのだと思いますか?
(百市)こういう場合は、やっぱり地球の温暖化とかが関係してくるのですか?
(太田)はい。集中豪雨と短時間大雨のトレンドラインを一致するトレンドラインがあります。
それは「日本近海の海面水温の変化」、日本近海における、2023年までのおよそ100年間にわたる海域平均海面水温(年平均)の上昇率は、+1.28℃/100年です。 この上昇率は、世界全体で平均した海面水温の上昇率(+0.61℃/100年)よりも大きく、日本の気温の上昇率(+1.35℃/100年)と同程度の値です。
このトレンドラインと集中豪雨、短時間大雨のトレンドランドは非常に近いのです。
やはり、よく言われている通り、日本近郊の海水温の上昇と、集中豪雨、短時間大雨の発生、線状降水帯の発生はリンクしているということが言えるわけです。
(百市)ということは日本近海の海水温が上昇するにつれ、線状降水帯の発生の頻度が今度も増えるという事が言えるわけですか?
(太田)そうです。
長期的傾向では1976年と2020年を比較すると、集中豪雨と短時間大雨の発生回数は2・2倍になったという話がありました。
その間特に頻度が上がったのが「梅雨時期」の集中豪雨の発生頻度なのですね。
年平均が2・2倍なのに対して、梅雨時期の集中豪雨の発生頻度はおよそ3・8倍増えています。
年間の中での梅雨時期の危険度がかなり増しているという事が言えるわけです。
(百市)まさに今の時期、気をつけなくてはいけないわけですね。
(太田)そうです。しかも一番怖いのは梅雨末期のこの時期です。
福岡県で過去6回大雨特別警報が出されていますが2017年が7月5日、2018年が7月6日、2019年は8月28日、2020年が7月6日、2021年は8月14日、そして2023年が7月10日6回中4回が7月5日から7月10日までの間に出されています。
とにかく今の時期、線状降水帯による大雨災害に気をつけるようにしてください。
(百市)しかもほぼ毎年出されていますよね。
この原因とされている地球温暖化は今すぐに解決するとは思えないので、今後このリスクと付き合っていかないといけない危機感をしっかりもっておきたいですね。
KBCラジオ みんなで防災 今週は「線状降水帯について考える その4」をお送りしました。
太田さん来週は?
(太田)線状降水帯発生情報についてお伝えします。
の動画一覧