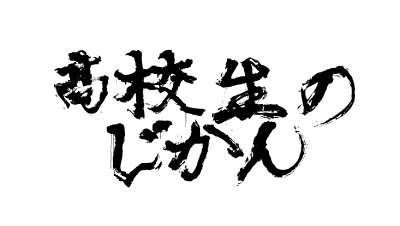現代の心の友 ChatGPTで「脳の衰え」を招く!? 専門家が指摘する3つの懸念と対策
福岡|
10/01 10:00

KBC「アサデス。ラジオ火曜日」にお届けした、KBCの近藤鉄太郎アナウンサーと、(株)Fusic 副社長・浜崎陽一郎さんが現代の”心の友”ともいえる「ChatGPT(生成AI)に潜む、「脳の衰え」に関する衝撃的な話題をピックアップして解説しました。
「今日は生成AIのお話をしたいんですけども、コンテツさんも心の友とおっしゃっているChatGPT。
ウォールストリートジャーナルからの記事なんですけども、ChatGPTで脳が衰えるんじゃないかという、お話があるんですよ。」
近藤アナが「仕事のサポートになる」と語る一方で、AIの利用が人間の認知機能に与える影響についての懸念が示されていました。
【「もう衰えてるじゃないですか!」:AIに丸投げで失う「達成経験」】

浜崎陽一郎さんがまず指摘したのは、AIに作業を丸ごと肩代わりさせることによる「自分で考え、組み立てる力」の低下です。
「いわゆる作業を丸ごとAIに肩代わりさせるわけですよね。『これやって、あれやって』と。そういったところが、どんどんどんどん衰えていきますよ」
「(AIが使えなくなったら)ちょっと不安になる」と近藤アナが漏らすと、
「それですよ!ほら、もう衰えてるじゃないですか!」と浜崎さん。
ある大学の研究では、AIを使って問題を解かせた学生は短期的な成績は良かったものの、最終的にその後のテストでAIを使わないと自力で解いた学生の方が成績が良かったという結果が出たと言います。
短期的には解けたなという感覚になっちゃうけれども、それは解けたという結果だけであって、中身のプロセスを実はあんまり 覚えてない。
AIで「解けた」という結果だけが得られ、プロセスを経験できないため、脳の成長に必要な「達成経験」が失われることが問題視されています。
浜崎さんは「筋トレと同じく、使わないと衰える」と述べ、まずは「自分で考えることをちょっとしてから使ったらどうですか」と提案。
意識的な「自力での思考」が重要だとしています。
【「結果だけがすごい薄い記憶になる」:検索プロセスを失うことの代償】

2つ目は、記憶力の低下です。
これはカーナビやGPSの利用による「空間記憶の低下」と似た現象だといいます。
「ワンクリックですべてを説明してくれているため、そのプロセスを調べることで記憶って脳に定着していくんですけども、もう結果だけが記憶として得られるがため、結果として、それだけがすごい薄い記憶になる」
情報を自ら集め、整理し、結論を導くという「プロセス」こそが脳に記憶を定着させてきました。
AIが完璧な答えを一瞬で提供することで、この「プロセスの蓄積」がなくなり、記憶が薄くなってしまうという懸念です。
この問題への対策として有効なのが、ChatGPTへの「問いかけ方」の工夫です。
単に「答えを教えて」ではなく、「解決できるように導いて」と質問を投げることで、自ら考える余地を残す「導き型質問」が学習効果を高めることがわかっています。
【「鵜呑みにしちゃうんですよね」:AI依存が招く「批判的思考」の衰え】

そして3つ目は、批判的思考力の低下です。
通常、人は情報源に対し「これ本当ちゃんと言ってるのか?」「この論調は正しいのか?」と批判的に吟味します。
しかし、ChatGPTの答えに対しては、「批判的に見る裏付けがないから鵜呑みにしちゃう」傾向があると浜崎さんは指摘しました。
AIが間違い(ハルシネーション)を起こしていても、「まあ言ってるし、大丈夫だろう」と信じてしまうことで、AI的な偏りを信じ込み、思考が衰えていくという懸念です。
AIの答えが出た後、「いかに自分がその答えに対する検証をするか」という作業が解決法として大事になります。
そして最後に浜崎さんが示した究極の解決策を示しました。
「使わない」
あるいは、「AI断ち」を1時間、あるいは1日してみるだけでも、効果はあるといいます。
浜崎さんは、電車賃や釣り銭の計算をしなくなった現代と重ね合わせつつ、「ChatGPT時代においてもですね、ちょっと脳を鍛えるってことをしたらどうかな」と提言し、対談を締めくくりました。