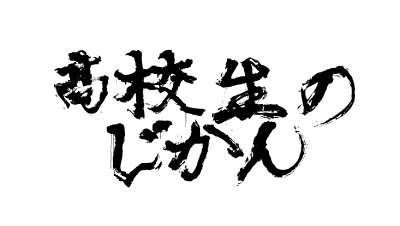番組概要
終戦から80年―
戦争を知る世代は年々減り続け、日常生活でその悲劇に触れる機会はほとんどない。
子どもたちにとって、日本の戦争は大昔に起きた歴史上の出来事。
それどころか、スマホやパソコンゲームでは戦闘がその題材になっている。
バーチャル空間で戦争がエンタメ化する一方、世界ではリアルな戦争が後を絶たない。
こうした中、迎える終戦80年の節目の夏。
番組ではリアリティを持って戦争と平和について考えられる企画を展開する。
現代の生活を戦時下と比較することで、80年前、たしかに私たちが暮らすこの場所にも戦争があったことを実感し、戦争が私たちの暮らしから何を奪うのかを考える。
番組内容
第1章 戦争と動物
戦時下の動物園を支えた飼育員たち
戦争の犠牲になったのは人間だけではない。
戦争により、人間の都合によって、多くの動物たちも犠牲になった事実がある。
福岡市動物園など県内や全国の動物園では、戦況が悪化して餌の確保が困難になったことや空襲による獣舎の破壊で猛獣が逃げ出すことへの懸念などから飼育されていた動物たちが殺処分された。
福岡市動物園ではそうした悲劇を忘れないため、当時動物園があった福岡市東区の馬出小学校に当時の正門のレプリカが設置されている。
また、到津遊園(現到津の森公園)の殺処分を題材にした絵本が出版され、その事実を後世に伝えている。
人間の都合に振り回され、犠牲になった動物たちが福岡にもたくさんいたということ、戦時中も懸命に動物たちに向き合った飼育員たちがいたという事実を「さすらいの獣医師」でお馴染みの外平友佳理氏とともに伝える。
ナビゲーター:外平友佳理(アサデス。KBC「さすらいの獣医師」)出演中)


第2章 戦争とスポーツ
福岡に1年だけ存在した幻のプロ野球球団
リーグ連覇と5年ぶりの日本一に向けて勢いづくソフトバンクホークス。
今でこそ、プロスポーツとして確固たる地位を築いたプロ野球だが、戦時中は違っていた。
1936年から7球団によるプロ野球リーグ戦がスタートし、沢村賞で有名な沢村栄治など名選手が誕生した。
しかし、戦況が悪化すると名選手でも特別扱いなしに「赤紙」が届き、出征した。
その結果、戦死する選手も後を絶たなかった。
こうした太平洋戦争の真っ只中の1943年、福岡に1年間だけ幻のプロ野球球団が存在していたことはほとんど知られていない。
その名も「西鉄軍」。
秋季リーグに優勝するも戦況の悪化で、翌年には選手の確保がままならずに解散してしまった。
戦時中ということもあり、「西鉄軍」に関する記録はほとんど残っていないが、わずかに残された手掛かりや関係者らへの取材を通して、戦時中のプロ野球が置かれていた状況を描くとともに、スポーツを通して戦争と平和について考える。
ナビゲーター:西田たかのり・松下由依(アサデス。KBC「スポーツ キラリ」)

第3章 戦争と天気予報
戦時中 消えた天気予報が急成長したワケ
台風シーズンの8月は1年で最も天気予報が気になる時期だ。
しかし、80年前の夏、終戦まで、日本から天気予報は消えていた。
1941年12月8日、日本による真珠湾への奇襲攻撃のまさにその日から天気図には軍事機密を表す印鑑が押された。
軍事オペレーションを行う上で気象情報は必要不可欠な要素だ。
「気象管制」といわれ、気象に関わる全ての情報は極秘とされた。
天気予報が消えたことで、日常の不便さにとどまらず、命を脅かす事態も起きていた。
台風や大雨のシーズンには防災を大々的に呼びかけられず、多くの人が命を落としたという記録も残っている。
一方で、軍事目的での天気予報技術の開発に各国が力を入れたため戦時中、日本をはじめ世界の予報技術は急発達した。
実際に風船爆弾など、気象条件にもとづく兵器も使用されている。
気象庁や福岡管区気象台に残る記録、気象庁の元予報官の証言などをもとに、天気予報を通して平和について考える。
ナビゲーター:佐藤栄作(アサデス。KBC 気象予報士)

第4章 戦争と娯楽
戦禍の子どもたちを笑顔にしたものとは
スマホアプリやテレビ、コンサートやテーマパークなどエンターテインメントが多様化し、今、子どもたちはたくさんの“楽しみ”に囲まれている。
しかし戦時中、娯楽は「不要不急」とみなされ、制限がかけられていた。
「娯楽=贅沢」とされ「楽しむ」こと自体が「非国民的」とされ非難の対象になる社会の空気だった。対戦国であったアメリカやイギリスの映画や音楽は禁止、英語も禁止、カタカナ語も使えなくなった。
ラジオから流れる歌は国威発揚や戦意高揚を促す軍歌ばかり。
漫画雑誌の表紙はもちろん、内容は娯楽や恋愛などのテーマは減り、戦争美化や忠義を描く内容にシフトした。
そんな中で、子どもたちはどんな楽しみ方をしていたのか、当時を知る人たちへ取材する。
また、80年前に子どもたちに大人気だった紙芝居を今の同年代の子どもたちに読み聞かせ、反応を探る。
戦争でその存在さえも否定された娯楽。
彩を失った社会はどうだったのか、その時代を生きた人々の証言とともに描き、エンターテインメントを通して戦争と平和について考える。
ナビゲーター:こだマン・山下七子(アサデス。KBC「芸能オッショイ!」)


第5章 戦争と学校
子どもたちはどんな授業を受けていたのか
戦時下を生きた子どもたちはどんな授業を受け、どんな学校生活を送っていたのだろうか。
その手掛かりになる貴重な資料が残されていた。
鹿児島県奄美群島にある徳之島で新人教師だった男性が残した「学級経営案」と書かれた資料。
読み解くと、現在の個性を大切に育み、多様性を重んじるという教育とは正反対の「国のために忠誠を誓う」という全体主義的な教育方針であったことがわかる。
地理や歴史の授業計画などにも戦争の影響が色濃く出ていた。
一方で、新人教師ながらその職業に懸命に向き合い、奮闘した姿を読み解くこともできる。
この「学級経営案」をつくった男性教師はその後、特攻隊員として出撃し戦死したという。
本企画では資料から戦時下の学校生活を読み解くとともに、戦時下で教師という職業に奮闘した1人の教師像から戦争が子どもたちに与えた影響について考える。
ナビゲーター:岡田理沙(アサデス。KBC 月曜ニュース・金曜MC)

出演者
<MC>
-
 宮本啓丞
宮本啓丞 -
 徳永玲子
徳永玲子
<ナビゲーター>
-
 岡田理沙
岡田理沙 -
 佐藤栄作
佐藤栄作 -
 こだマン
こだマン -
 山下七子
山下七子 -
 西田たかのり
西田たかのり -
 松下由依
松下由依