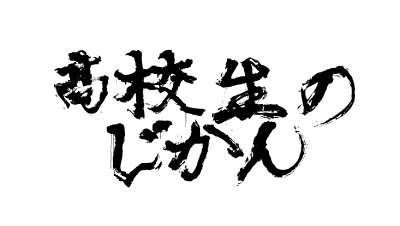【 小倉織❶ 】「紡ぎ、繋ぐ」染織家 築城則子さん
放送内容
2025年07月27日
密度の濃い経糸(たていと)が特徴で、その丈夫さから江戸時代の武士に袴や帯として愛用されていたという小倉織。
明治時代には、その袴は男子学生たちに重宝されていました。
しかし、昭和初期に入り、生活様式の変化、洋服の普及、生産者の減少などもあって、小倉織は途絶えました。
北九州市八幡東区に工房を構える遊生染織工房。
主宰の築城則子さんは、40年ほど前に骨董品店で出会った一枚の端切れに強いインスピレーションを感じたと思い出を語ります。
染織家としてそれまでも世界中の様々な生地を調べていた則子さんでしたが、自分の地元に、丈夫でつやのある美しい織物、「小倉織」の存在があったことを、このとき初めて知ったと言います。
「小倉織を復活させたい」。この古い端切れこそが「自分の先生である」と研究を重ね、1984年についによみがえらせることができました。
小倉織の特徴はその経糸(たていと)にあります。
途絶える前の小倉織の場合、経糸の密度は、緯糸(よこいと)の2倍ほどだったそうです。
則子さんは、緯糸の3倍もの経糸をより合わせて、より滑らかで、洗練された新しい小倉織を確立しました。
経糸はいったん織り始めるともう変えることができません。
経糸を決める作業に自身のすべてをかける、と則子さんは言います。
そして経糸が決まってしまえば、「緯糸は感情をぶらさずに、ただ一心に織るだけ」と、職人としての気構えを教えてくれました。
則子さんが小倉織を再興してから40年ほど経過し、そのバトンは現代の小倉織の作家たち、そして則子さんの娘、弥央さんに繋がれています。
海外では「Kokura Stripes」と称され、年々そのプレゼンスが高まっている小倉織。
則子さんは「世界に通用する織物」だと断言します。
一度は途絶えた小倉織を復活させた則子さんの願いは、世界中の人たちに小倉織を使ってもらうこと。その願いを娘である弥央さんに託しています。
「今の時代の人が使わないと続いていかない」、手織りの織機に向かう則子さんの姿からは、一度は途絶えた「文化」を引き継いだものとしての強い覚悟と責任を感じさせます。
小倉織を再興し、新しい小倉織を紡ぎ続ける則子さんにとって、日本の原風景ともいえる里山の景観を残す「八幡東区猪倉地区」は、大切な場所だと言います。
そのシンボルである大楠のそばに座り、木もれ日をただ見ているだけで、新たなアイデアが浮かんでくることがあるそうです。
の動画一覧