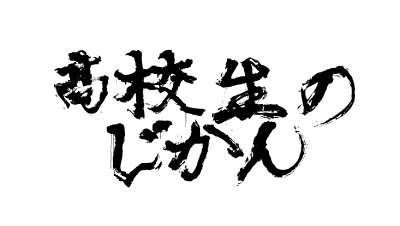「台風」について
番組で紹介した情報
2025年07月29日
(太田)KBCラジオ ヒルマニ 後半のこの時間は「みんなで防災」をお送りします。
ヒルマニ火曜日後半戦
きょうは「KBCラジオ みんなで防災」をお送りします。
KBC防災ネットワーク主幹兼解説委員の太田祐輔です。
スタジオには引き続き加藤 恭子アナウンサーです。
猛暑が続いていますが、最近の天気予報を見ると台風の情報をよく聞きます。
(太田)きょうはその「台風」について考えます。
(太田)台風に関しては「強い台風」とか「非常に強い台風」「猛烈な」という強さの表現があります。
これってどういう基準になっているのかですが。
(加藤)風の強さですよね。
(太田)「強い」台風は、最大風速が33メートル毎秒以上44メートル毎秒未満。
これは時速にすると約119キロメートルから158キロメートルに相当します。
「非常に強い」台風は、最大風速が44メートル毎秒以上54メートル毎秒未満。
時速では約158キロメートルから194キロメートルです。
そして、最も危険な「猛烈な」台風は、最大風速が54メートル毎秒以上です。
これは時速にすると194キロメートルを超える、まさに新幹線並みの速さの風が吹く状態です。
(加藤)時速にすると、その凄まじさがより実感できますね。
あとは大きさを表す指標もありますよね。
(太田)「大型の」とか「超大型の」それは「大きさ」を表す指標で、風速15メートル毎秒以上の風が吹く範囲、つまり強風域の半径によって分類されます。
「大型の」台風は、強風域の半径が500キロメートル以上800キロメートル未満。
「超大型の」台風は、強風域の半径が800キロメートル以上です。
台風は、同じ強さでも大きさが異なると、影響の範囲が大きく変わってきますので、この「大きさ」も非常に重要な情報です。
(加藤)ずっと前は「弱い」とか「小型の」という表現もありましたよね。
(太田)そうなんです。2000年6月にそういった表現は廃止されています。警戒しなくてはいけないのに「小型」とか「弱い」と聞くと安心情報になってしまうことも検討の理由になったようです。
(加藤) 強さと大きさ、この二つの情報に注目することが大切なのですね。では、これらの情報を踏まえて、私たちはどのように備えるべきでしょうか?
(太田)はい。まず、最も重要なのは、「早めの情報収集と避難行動」です。
梅雨末期の大雨などはいつどこで災害級の雨になるのか予想が非常に難しいところがあります。
それと比較すると台風は事前に予想することができる危機です。
テレビやラジオ、インターネットなどで常に最新の台風情報を確認しましょう。
特に、気象庁が発表する「警報・注意報」はもちろん、「特別警報」が発表された場合は、これまでに経験したことのないような甚大な被害が予想されますので、命を守る行動を最優先してください。
(加藤)台風に伴う特別警報ってどういう時に出されるのでしょうか?
(太田)大雨特別警報: 台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表されます。特に警戒すべき事項を明示するため、「大雨特別警報(土砂災害)」「大雨特別警報(浸水害)」のように発表されることもあります。
暴風特別警報: 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、暴風が吹くと予想される場合に発表されます。
こういった情報が出されたら事前に避難するなど防災行動をとってください。
自治体が発表する「避難情報」にも注意し、自分がいる場所が危険な場所である場合は指示に従って早めに避難することが命を守る上で非常に重要です。
(加藤)ほかに備えることはありますか。
(太田)水の確保と食料の備蓄: ライフラインが寸断されることも想定し、3日〜1週間分の水と食料、非常用トイレなどを準備しておきましょう。
窓ガラスの飛散防止: 強い風でガラスが割れるのを防ぐため、雨戸やシャッターを閉める。ない場合は、カーテンを閉め、窓に飛散防止フィルムを貼るか、ガムテープを貼るなどの対策を。
屋外の飛散物の固定・撤去: 植木鉢、物干し竿、ゴミ箱など、風で飛ばされそうなものは家の中に入れるか、しっかりと固定しましょう。
排水溝の点検と清掃: 大雨による浸水被害を防ぐため、自宅周辺の排水溝や雨どいに落ち葉などが詰まっていないか確認し、清掃しておきましょう。
非常用持ち出し袋の準備: 貴重品、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリーなどをひとまとめにして、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。
家族との連絡方法の確認: 万が一、離れ離れになった場合の集合場所や連絡手段を事前に話し合っておきましょう。災害用伝言ダイヤルなども活用できます。
(太田)台風が近づいて備えるのではなく、今のうちに飛散防止シートなどは買っておくのもいいかもしれません。
あといつも言ってますね。
何よりも大切なのは「ハザードマップの確認」です。
ご自宅が土砂災害警戒区域や浸水想定区域に入っていないか、事前に確認し、避難経路を把握しておくことが非常に重要です。
(太田)それと最後にもう一つ、台風接近時が「高潮」への警戒も必要です。
高潮(たかしお)とは、台風や発達した低気圧が接近することによって、通常の満潮時の潮位よりも海面の水位が異常に高くなる現象を指します。波が高いこととは異なり、海面そのものが全体的に持ち上げられるイメージです。
・気圧低下による吸い上げ効果
台風や低気圧の中心付近は、周りの気圧よりも非常に低くなります。
この気圧の低い場所では、海面を押さえつける力が弱まるため、海水が吸い上げられるように持ち上がります。
気圧が1ヘクトパスカル(hPa)下がると、海面は約1センチメートル上昇すると言われています。例えば、中心気圧が950hPaの台風が来た場合、通常の気圧(約1013hPa)に比べて海面が約60cmも高くなる可能性があります。
・風による吹き寄せ効果
台風や低気圧に伴う強い風が、沖から海岸に向かって吹き付けることで、海水が海岸に吹き寄せられ、海岸付近の海面が上昇します。
特に、奥に行くほど狭まるV字型の湾などでは、吹き寄せられた海水が集中し、さらに水位が高くなりやすくなります。
護岸や防潮堤を乗り越えて海水が市街地に流れ込み、広範囲にわたる浸水が発生します。特に海抜の低い「ゼロメートル地帯」では、一度浸水すると水がなかなか引かず、長期間浸水状態が続くことがあります。
過去には、1934年の室戸台風や1959年の伊勢湾台風、2018年の台風21号など、高潮によって甚大な被害が発生した事例が多数あります。
台風による高潮にも警戒してください。
(太田)ヒルマニ火曜日後半戦 きょうは「台風にどう備えるか」についてお送りしました。
の動画一覧