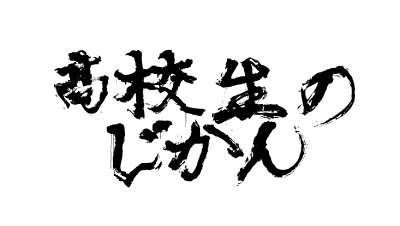復旧はいつ?損傷した下水道管の修復方法とは【埼玉・八潮市の道路陥没】
社会|
02/01 22:30
雨が救助活動にどう影響するのでしょうか。道路陥没事故発生から5日目。埼玉県八潮市の現場では、重機が入るためのスロープが完成しましたが、作業を妨げる新たな障害も。(2月1日OA「サタデーステーション」)
■スロープ完成も「水」で作業中断
報告・仁科健吾アナウンサー(1日午後7時半頃)
「2台の重機による作業が続けられています」
現場の作業は、ようやくスロープ作りから本格的な救助活動へ。しかし、困難を極めています。
報告・仁科健吾アナウンサー(1日午後8時半頃)
「消防の発表によりますと、きょうの重機による作業(穴に関わる部分)は中断することが決定しました」
中断の理由は「水」です。
報告・小林匠カメラマン(1日午前11時頃)
「地面の中から湧き水のように水が湧いているようにも見えます」
現在はこの水の影響で重機を使った作業ができず、中断を決めたといいます。埼玉県では2日から3日にかけて、雨や雪が降る予報にもなっています。
2日前から作業が進んでいた、穴の底へ重機を下すためのスロープ作り。大きな障害になっていたのが、2つめの穴が開いた時から宙に浮いた状態になっていた電柱でした。しかし、1日午前3時半ごろに取り除かれ、1日朝、当初の予定よりも10時間ほど前倒しでスロープが完成。救助隊員とみられる人が、穴の底を確認しにいく様子もみられました。
報告・仁科健吾アナウンサー(1日午前11時半頃)
「報道陣が初めて規制線の中に入っていきます。雨水管と呼ばれる四角い管が見えてきました。少し、泥のような、下水のような臭いもします」
1日の昼前には、初めて、報道陣が現場近くまで入ることが許可されました。
報告・仁科健吾アナウンサー
「道路の一部でしょうか?重機が大きなコンクリートの一部を中段部分まで運び出します。その後は、地上にいる重機が地上の方へと運び出します。二段階に分けて作業が行われています」
1日から、がれきを砕くための重機も投入。しかし、その後、現場に爆発音が響き渡りました。
報告・仁科健吾アナウンサー
「大きな音がしました。今、重機の一部が破損しました。そこからオイルのようなものが出てきています」
作業開始からわずか6分で重機が故障する場面もありました。埼玉県の大野知事はスロープの中腹まで降りて現場を視察。
埼玉県
大野元裕知事
「非常に難しい状況にあるということを改めて確認いたしました」
■120万人に影響続く
下水道マップをみると、埼玉県東部で排出される下水の大部分が、今回穴が開いた下水道管を通ることがわかります。そのため、およそ120万人に下水道の使用自粛を呼びかけるという、異例の事態が続いている状況です。
一方、3日前から下水の緊急放流が行なわれているポンプ場。事故現場から16キロほど離れた場所にあり、上流から集まる下水の一部をここから川に放流することで現場への流入量を減らしていますが…
報告・富樫知之ディレクター
「少し風が吹くと川のほうから下水のような臭いを少し感じますね」
埼玉県による水質検査でも、かすかな下水臭が確認され、「魚が死んでいる」との報告も上がっています。ただ、下水道の使用自粛については1日、解除の条件が初めて示されました。
埼玉県
大野元裕知事
「(下水道管の)応急補修に入ってから、想定通りだと、約1週間で、下水等の使用自粛を取りやめることができる」
救助活動が終了してからおよそ1週間後、風呂や洗濯への制限が解除される見通しです。現場周辺で避難を続ける住民も、近いうちに自宅に帰れる可能性が出てきました。
ガス管が爆発するリスクがあったことが、周辺住民に避難を呼びかけた一番の理由でしたが、ガスは1日午前9時ごろに全面復旧しました。
■総延長“地球12周分”点検に課題
今回の陥没事故を受け、国交省は、東京など7都府県に対して、下水道管の緊急点検を要請。7日までの報告を求めています。
一方で、取材して分かったのは、こうした点検にかなりの時間を要するということです。下水道管の中は硫化水素が発生するため、人は立ち入らず、カメラ付きロボットを走らせて確認する方法が一般的です。八潮市の陥没現場を通るような巨大な下水道管では、水上走行型のカメラを使用するといいます。全国の下水道管の総延長距離はおよそ49万キロメートル。地球12周分の長さです。17年後には、およそ4割が寿命を迎えるといいますが…。
カンツール
佐々木啓至さん
「1日280メートルというのが一般的な日進量。老朽化する管は増えていく、49万キロメートルを見なければいけない、いろんな課題が積み重なっているのかなと思います」
■下水道管に亀裂入れば「数時間で陥没も」検証実験
下水道管に穴が開いた場合、わずかな時間で陥没事故が起きる可能性もあると言います。桑野教授は、模型を使った実験で陥没のメカニズムを検証しました。その結果を実際の道路に置き換えると…
東京大学生産技術研究所
桑野玲子教授
「条件次第ですけれども、亀裂が入って土砂流出が継続的に起こったら、数時間で陥没に至るという可能性はあります」
その条件とは、下水道管の「老朽化」、「亀裂の大きさ」、「地下水の水位」など。そして、被害を大きくしたのが“深さ”と“地盤”です。
東京大学生産技術研究所
桑野玲子教授
「深さ10メートルのところにあったので、それは亀裂が入った場合に空洞が大きく成長してしまう要因になります。それから、周りの“地盤が砂”なので、やはり空洞が成長しやすい条件になります」
深い下水道管は、各地にありますが地表からの調査には、限界があります。
東京大学生産技術研究所
桑野玲子教授
「地中レーダー探査だと深さが2mあるいは3m程度までしか届きませんので、今回の深さの空洞を見つける手段というのは、今のところありません」
■下水管の修復方法の1つ「SPR工法」
下水道管に穴が開く前に補修することはできないのでしょうか?
日本SPR工法協会
岡野敏彦技術部長
「今ある下水管の内側に、新しい管をつくる方法があります。SPR工法と言います」
地上のマンホールから修復が必要な下水道管の中へ硬質塩化ビニル製の帯をどんどん入れていき、下水道管の内側にらせん状に巻いていくことで、一回り小さな下水管を作ります。さらに、隙間を埋めることで、元々の下水道管と一体化。これで50年程度の延命が可能になると言います。
日本SPR工法協会
岡野敏彦技術部長
「道路を掘らないため、交通への支障も少なく工事ができる、 低コストで工事ができる。それから最大のメリットは水(下水)を流しながら施工できること」
しかし、今回の下水道管の復旧には使えない可能性が高いといいます。
■今回の下水道管はどう修復?
高島彩キャスター:
取り残されている男性の一刻も早い救助が待たれますが、その後の復旧作業、どうなっていくのでしょうか?
板倉朋希アナウンサー:
2016年に福岡の博多駅前で起きた道路陥没事故の場合、縦横30メートル深さ15メートルにわたり陥没し水道管やガス管通信ケーブルなどが破損。陥没の原因は地下鉄の延伸工事によるトンネルの崩落だと推定されていて、今回の八潮の現場とは異なりますが、崩落規模は今回の八潮が、約40メートル、深さ15メートルということで、同じような状況になっています。ただ福岡では復旧作業を僅か1週間で終えています。
高島彩キャスター:
随分と早いと思いますが、今回の現場ではどうなのでしょうか?
板倉朋希アナウンサー:
その点、福岡の事故の際に道路陥没に関する検討委員会のメンバーとして復旧に携わった福岡大学・佐藤研一教授に聞きました。「博多の復旧作業については陥没から僅か7時間後に復旧作業が始まったんですが、この時は要救助者がいなかったので、今回はまずは救助活動をしなければならないので、復旧までの時間は見通せない状況なんじゃないか」ということでした。また、八潮市の現場周辺で使用自粛の要請が出ている下水道管の修復については、「博多の時は下水道管の直径が約2メートルということで、それほど大きくなかったので、破損した部分を新しいものと交換するということでできましたが、今回の八潮市の場合は、下水道管の直径が約5メートルと、かなり大きいので、これを交換するということはなかなか難しい状況」ということなんです。
高島彩キャスター:
埼玉県からは修復方法について、どんな発表があったのでしょうか?
板倉朋希アナウンサー:
まず穴に溜まった土砂や瓦礫を撤去して人命救助をするというのが第1段階ですが、そのあと損傷している下水道管の穴を固い水飴のような素材でフタをして、そのあと水を通さないジェル状の材料を使って応急補修をして砂や土で埋め戻す、といった流れになるようなんです。
高島彩キャスター:
あくまでも応急補修ということですよね。では、この地域の方たちが通常の生活に戻るまでにはどのくらいかかるのでしょうか?
板倉朋希アナウンサー:
埼玉県によりますと「下水道管の修復作業を始めてから1週間をめどに、下水道の使用自粛を解除したい」としていますが、瓦礫の状況や下水道管の破損状況しだいで、もっと時間がかかる可能性もあるということでした。
高島彩キャスター:
まずは人命救助という段階ではありますが、柳澤さんは、今回の崩落事故をどのようにご覧になっていますか。
ジャーナリスト柳澤秀夫氏:
下水道管の老朽化は全国共通の問題だといわれています。そうするとどこで起きるのか分からないという不安が拭えないと思うんですよ。であれば点検ということになるんですが、人手不足や予算の確保が難しいという課題がありますけれども、やはり人命が関わるし被害の大きさが広がると大変なことになるのは今回よく分かりましたから、「一体どうすればいいのか?」という待ったなしの重い課題を突きつけられていると思います。